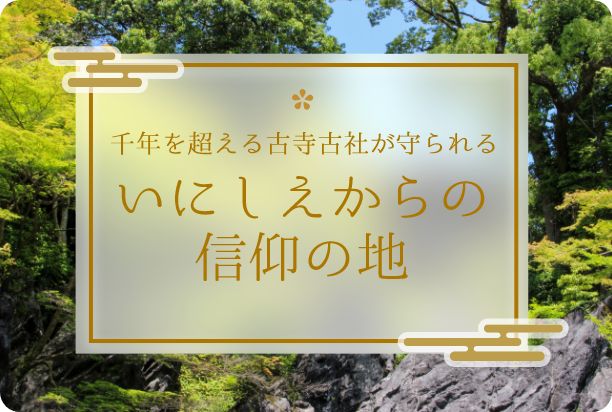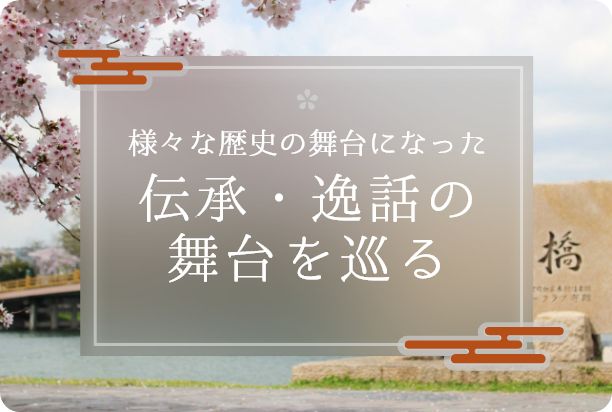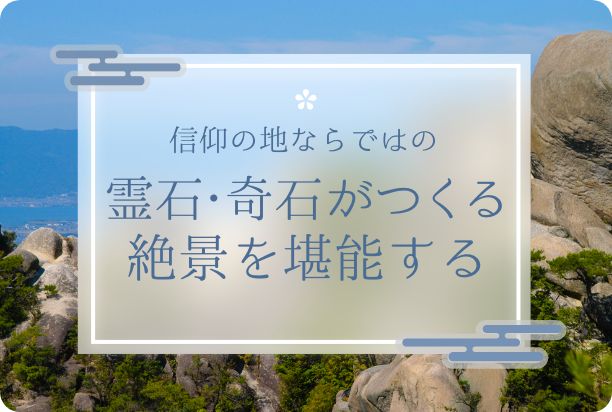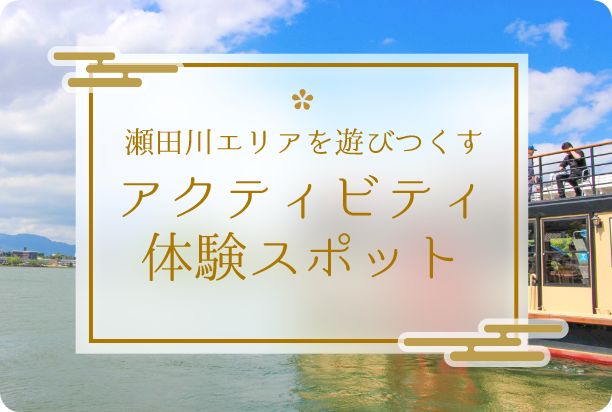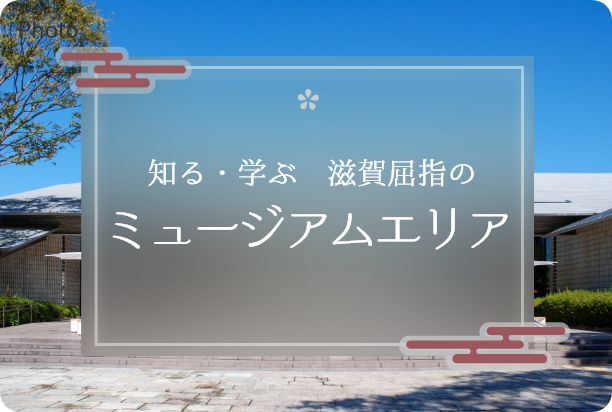瀬田川流域には古くからの伝承・逸話が残る地が数多く残っており、
歴史ファンならずとも必見です。
雅な平安時代や、群雄割拠の戦国時代に、しばし思いをはせてみては?
戦国武将が目指した瀬田の唐橋

日本三名橋の一つで近江八景「瀬田の夕照」で名高い名橋。古くは、瀬田橋・瀬田の長橋とも呼ばれ、日本書紀にも登場します。
現在の状態(大橋・小橋)は織田信長によって整備されたものです。
戦国時代、「唐橋を制するものは天下を制す」とまでいわれるほど、京都へ通じる軍事・交通の要衝であることから幾度となく戦乱の舞台となりました。かの武田信玄も死の淵に際し、「我が軍旗を唐橋に立てよ」と言ったと伝わっています。
また、風の強い日に琵琶湖を船で渡るより、回り道をしても唐橋を渡った方が安全だということから、「いそがばまわれ」の語源となったエピソードでも有名です。
-
京阪電鉄 石山坂本線「唐橋前駅」下車 徒歩5分/JR琵琶湖線「石山駅」下車 車5分
-
国道1号。名神高速「瀬田東IC」から10分、又は「瀬田西IC」から5分
俵藤太の百足退治伝説 瀬田の唐橋と雲住寺
雲住寺 http://otera.jodo.or.jp/temple/28-392/ 三井寺(弁慶の引き摺り鐘) http://www.shiga-miidera.or.jp/about/legend01.htm
平安時代中期の貴族、豪族、武将である俵藤太(本名:藤原秀郷)が、瀬田の唐橋で百足を退治したという伝説です。
醍醐天皇の時代、瀬田の唐橋に大蛇が横たわり、人々は怖れて橋を渡れなくなっていました。そこを通りかかった俵藤太は臆することなく大蛇を踏みつけて渡ってしまいました。すると大蛇は人に姿を変え、一族が三上山の百足に苦しめられていると訴え、藤太を見込んで百足退治を懇願しました。
藤太は強弓をつがえて射掛けたが、一の矢、二の矢は跳ね返されて通用せず、三本目の矢に唾をつけて射ると効を奏し、とうとう百足を倒しました。そのお礼として、米の尽きることのない俵や使っても尽きることのない巻絹などの宝物を贈られました。
竜宮にも招かれ、赤銅の釣鐘も追贈され、これを三井寺(園城寺)に奉納しました。これが有名な「弁慶の引き摺り鐘」として伝わり、今も大切に守られています。
唐橋の東詰にある雲住寺には百足の供養堂が建っています。また、唐橋小橋と大橋の間にある中洲には俵藤太像があります。
-
京阪電鉄 石山坂本線「唐橋前駅」下車 徒歩8分/JR琵琶湖線「石山駅」下車 車5分
-
国道1号。名神高速「瀬田東IC」から10分、又は「瀬田西IC」から5分
-
普通車 3 台
| 拝観料 | 無料 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
| 営業時間 | 事前に電話にて御連絡下さい |
| お問い合わせ | 雲住寺 TEL:077-545-0234 |
松尾芭蕉ゆかりの地 幻住庵

江戸時代に松尾芭蕉(1644-94)が隠棲(いんせい)をかね、4カ月間起臥した草庵。京阪電鉄石山寺駅の西にある国分山東斜面の近津尾(ちかつお)神社にあります。芭蕉が、ここでの生活を『幻住庵記(げんじゅうあんき)』に記したことはあまりにも有名です。
幻住庵は、芭蕉の門人の1人であった菅沼曲翠(すがぬまきょくすい)(1659-1717)が義仲寺で生活していた芭蕉の隠棲地として、伯父幻住老人(げんじゅうろうじん)(定知(さだとも))の旧庵に手を加えて、提供したものです。芭蕉は、ここからの眺望やここでの生活を心から愛しました。幻住庵の名は、曲翠の伯父幻住老人の名に由来しています。
今までは、近津尾神社境内に跡碑と句碑がひっそりと立っているのみでしたが、平成3年(1991)10月「ふるさと吟遊芭蕉(ぎんゆうばしょう)の里」事業の一環として幻住庵が再建され、『幻住庵記』の中に出てくる「とくとくの清水」は、現在も変わらずに木立ちの中を流れています。なお、句碑に刻まれているのは「先(まず)たのむ椎の木もあり夏木立」という『幻住庵記(げんじゅうあんき)』を結ぶ句です。
-
JR琵琶湖線石山駅から京阪バス国分下車、徒歩15分/京阪石山寺駅から徒歩30分
-
国道1号。京滋BP「石山IC」から10分
-
普通車10台、大型車3台
| 拝観料 | 無料 |
|---|---|
| 定休日 | 月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始 |
| 営業時間 | 9:30~16:30 |
| お問い合わせ | 幻住庵 TEL:077-533-3760 |
源氏物語起筆の寺 石山寺
https://www.ishiyamadera.or.jp/about/literature
平安時代寛弘元年(1004)、紫式部は時の中宮の新しい物語を読みたいというリクエストを受け、新しい物語を作るために石山寺に七日間の参籠をしていました。そのとき、琵琶湖の湖面に映える十五夜の名月を眺めて、都から須磨の地に流された貴公子が月を見て都を恋しく思う場面を構想し、「今宵は十五夜なりけり」と書き出したのが『源氏物語』の始まりだったといいます。世界文学の第一に挙げられる物語は、石山寺で誕生したのです。本堂の一角にある「源氏の間」は物語執筆の部屋といわれます。
-
京阪電鉄/石山坂本線「京阪石山寺駅」下車 徒歩10分/JR琵琶湖線「石山駅」下車 車5分
-
名神高速「瀬田東IC」・「瀬田西IC」・京滋BP「石山IC」から車で10分
-
普通車140台
| 入山料 | 600円(30名以上500円) |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
| 拝観時間 | 9:00~16:30(閉門) |
| お問い合わせ | 大本山 石山寺 TEL:077-537-0013 FAX:077-533-0133 |
かつて湖面に美しく姿を映した膳所城跡

近江大橋西詰のすぐ南側に突き出た地にあった膳所城は、徳川家康が関ヶ原の合戦の後、築城の名手といわれた藤堂高虎に最初に造らせた城でした。城構えは、湖水を利用して西側に天然の堀を巡らせた典型的な水城で、白亜の天守閣や石垣、白壁の塀・櫓(やぐら)が美しく湖面に浮かぶ姿は、実に素晴らしかったといいます。この美観は、「瀬田(せた)の唐橋(からはし)唐金擬宝珠(からかねぎぼし)、水に映るは膳所の城」と里謡(さとうた)にも謡(うた)われています。
戸田(とだ)・本多(ほんだ)・菅沼(すがぬま)・石川と城主が変わった後、本多6万石代々の居城として長く偉容を誇りましたが、明治維新で廃城になり楼閣(ろうかく)は取り壊されました。城門は重要文化財で、膳所神社や篠津(しのづ)神社に移築されて残っています。
現在、本丸跡は、膳所城跡公園として整備され、春には桜の名所として花見客を多く集めています。
-
京阪電鉄/石山坂本線 「膳所本町」 下車 徒歩7分/JR琵琶湖線 「大津」 下車 バス15分 膳所公園
-
名神大津ICから約10分
-
普通車10台
唐橋を守り続けた勢多城址

瀬田川東側に軍事上の目的で築城された城。瀬田川は琵琶湖から流れ出る唯一の川であり、瀬田川に架かる瀬田橋は「急がば回れ」の語源ともなった橋で、戦国時代は交通・軍事上の重要戦略拠点でありました。その瀬田橋のたもとにあった瀬田城も重要な位置を占めていたのです。
永享年間(1429〜1441年)の山岡資広(すけひろ)から始まり代々山岡氏が城主で、織田信長政権下の山岡景隆は、瀬田橋を守る城主として活躍、織田信長からの信頼が厚く織田信長は上洛のたびに瀬田城を宿所としていました。
天正10年(1582年)本能寺の変で織田信長を討った明智光秀は、安土城を占拠するため瀬田橋に軍を進めました。架橋を任されていた山岡景隆は織田信長への忠義を守り瀬田橋を焼き落とし明智光秀の軍を阻んだのです。これにより明智光秀はいったん兵を引かざるを得なくなり、天下の趨勢に大きな影響を与えたと言われています。
今は、瀬田唐橋の東側高層マンションの下の県道前にひっそりと城跡石碑が立っています。
-
京阪電鉄 石山坂本線 「唐橋前」 下車 徒歩5分
-
名神瀬田東(西)ICから約5分
浮世絵師が画題にした近江八景
「東海道五十三次」で知られる江戸時代の浮世絵師である歌川広重によって描かれたことで知られる滋賀県の8つの景勝地を総じて「近江八景」と言います。
戦国時代に公家や五山の詩僧によって選定されたとも、また1500年(明応9)前関白近衛政家と尚通の父子が選定したとも言われています。
この8つの景勝地のうち、「矢橋の帰帆」、「粟津の晴嵐」、「石山の秋月」、「瀬田の夕照」の4つはこのびわ湖の南もしくは瀬田川付近に集中しています。
広重が描いた浮世絵を見ながら、カメラ片手に廻ってみるのも楽しいかもしれません。
矢橋の帰帆
-
JR南草津駅西口より近江鉄道バス イオンモール草津行き(草津総合病院経由)「矢橋」下車 徒歩約6分
JR草津駅西口より南草津駅行き「矢橋北口」下車 徒歩約10分
粟津の晴嵐
-
JR琵琶湖線「石山」下車 徒歩10分
石山の秋月(石山寺)
-
京阪電鉄/石山坂本線「京阪石山寺駅」下車 徒歩10分/JR琵琶湖線「石山駅」下車 車5分
-
名神高速「瀬田東IC」・「瀬田西IC」・京滋BP「石山IC」から車で10分
-
普通車140台
瀬田の夕照(瀬田の唐橋)
-
京阪電鉄 石山坂本線「唐橋前駅」下車 徒歩5分/JR琵琶湖線「石山駅」下車 車5分
-
国道1号。名神高速「瀬田東IC」から10分、又は「瀬田西IC」から5分